皆さんが普段、街で見かける建設現場。そこでは、たくさんの職人さんたちが、暑い日も寒い日も力を合わせ、一つの建物をつくり上げています。しかし今、その現場のあり方が、少しずつ、だけれども確実に変わり始めています。
現在の建設業界では、長年にわたって、働く人々の高齢化や、これからを担う若い世代の人手不足といった、大きな課題を抱えています。また、より働きやすい環境をつくっていくことも、社会全体のテーマとなっています。こうした背景から、「すべての作業を現場で、ゼロから行う」という昔ながらのやり方を見直す動きが、静かに広がっているのです。
その新しい考え方の一つが、今回お話しする「工場製作(こうじょうせいさく)」です。
これは、建物の部品の一部を、あらかじめ専門の工場で丁寧につくり込んでおき、それを現場へ運んで組み立てる、という方法です。現場での複雑な作業をできるだけ減らし、工場での事前準備に力を入れる。この変化は、単に効率を上げるためだけのものではありません。建物の品質をより確かなものにし、現場で働く人々がより安全に、そして安心して仕事に取り組める環境をつくるための、未来に向けた大切な一歩なのです。
配管の「工場製作」とは、どのようなものでしょうか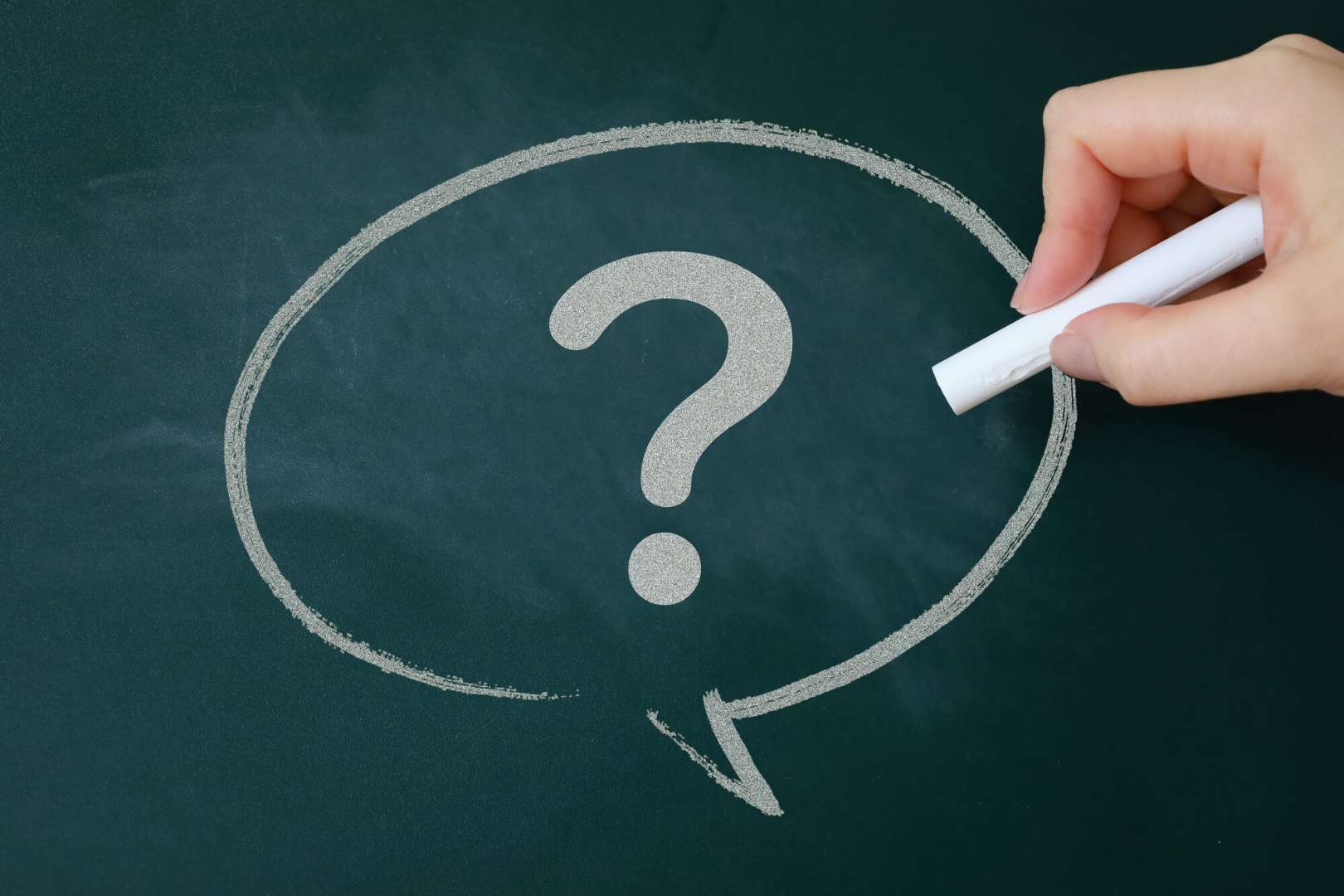
「工場製作」という言葉を聞いても、具体的にどのようなことが行われているのか、なかなか想像がつきにくいかもしれません。特に、建物の血管とも言える「配管」の工場製作は、建物の品質や工事全体の流れを大きく左右する、とても大切な工程です。ここでは、その流れを三つのステップに分けて、少し詳しく見ていきましょう。
まずはパソコン上で、精密な「立体図面」をつくる
昔の配管工事は、職人さんが紙の図面を見ながら、頭の中で配管の通り道を組み立て、現場で長さを合わせながら作業を進めるのが一般的でした。しかし工場製作では、まず初めに、パソコンの画面上で非常に精密な「立体(3D)の図面」を作成します。BIM(ビム)と呼ばれる特別な技術を使い、まるで建物のミニチュアを画面の中でつくるように、壁や柱、他の設備との位置関係を見ながら、配管がどこを、どのように通るのかを、1ミリ単位で正確に設計していくのです。この段階で、配管同士がぶつかってしまったり、通るスペースがなかったりといった問題点を、すべて事前に解決しておくことができます。
図面を基に、工場で「配管ユニット」を組み立てる
精密な立体図面が完成したら、その設計データは専門の工場へと送られます。工場では、そのデータを基に、配管の切断や曲げ加工、部品の取り付けといった作業が行われます。現場と違い、工場の中は天候に左右されることもなく、必要な工具や機械もすべてそろっています。熟練の職人さんたちが、明るく安全な環境で、一つの作業に集中して取り組むことができるのです。こうして、図面通りに正確に組み立てられた配管は、ある程度の大きさのかたまり、つまり「配管ユニット」として完成します。これはプレファブ(あらかじめ製作するという意味の言葉)とも呼ばれています。
完成したユニットを、現場へ「お届け」する
工場で丁寧につくり上げられた配管ユニットは、トラックに乗せられて、建設現場へと届けられます。現場では、すでに設置場所の準備が整えられており、クレーンなどを使ってユニットを吊り上げ、所定の位置へと慎重に取り付けます。現場での主な作業は、このユニットとユニットをつなぎ合わせること。これまで現場で行っていた、一本一本の配管を切ったり、つないだりといった複雑で時間のかかる作業が大幅に減るため、現場はとてもスムーズに、そして静かに工事を進めることができるのです。
みんなに「うれしい」三つの理由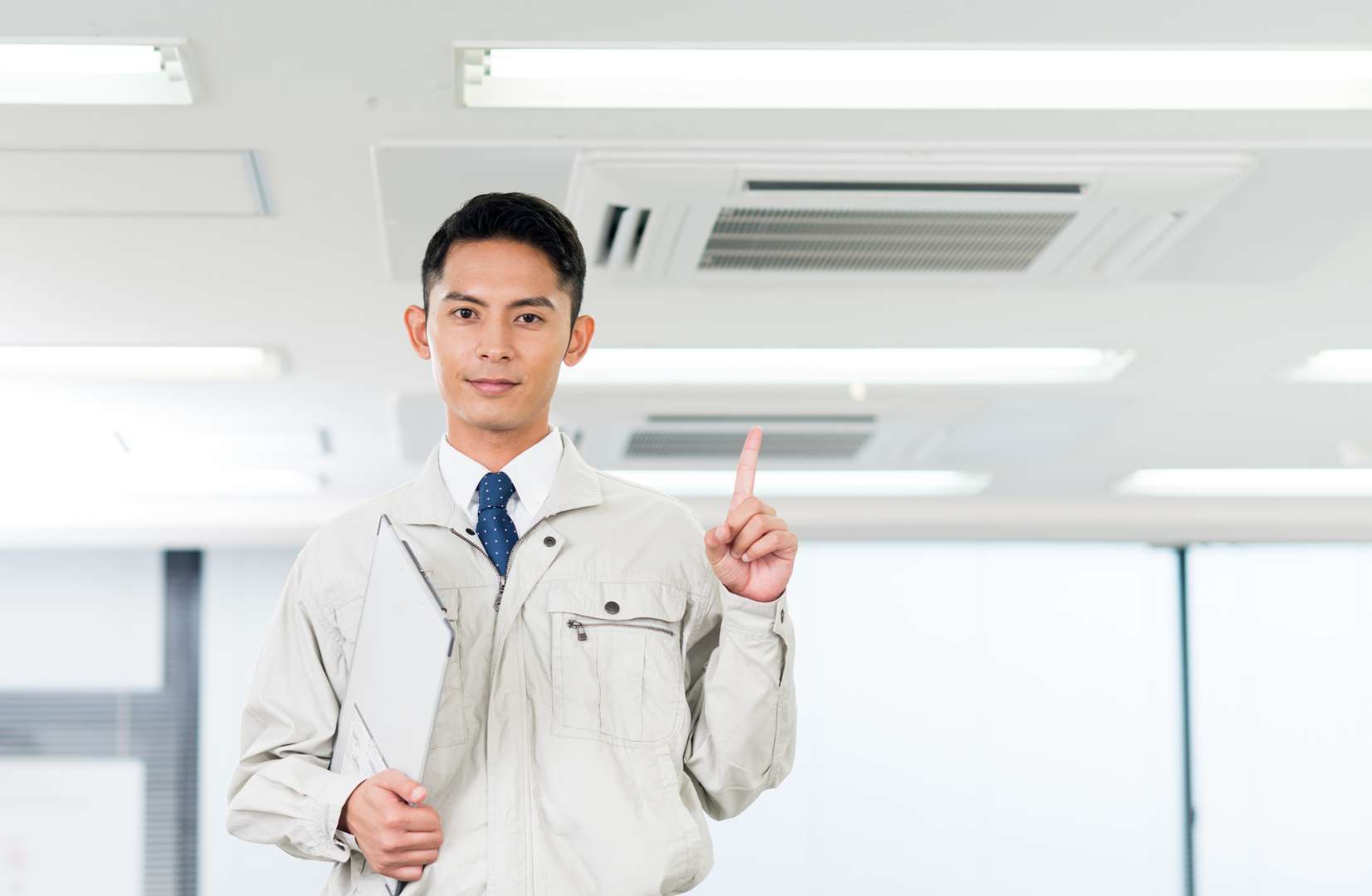
配管をあらかじめ工場でつくるという方法は、一見すると、ただ作業の場所が変わっただけのように思えるかもしれません。しかし、この変化は、建物を建てる人、使う人、そしてつくる人、そのみんなにとって、たくさんの「うれしい」ことにつながっています。
品質のばらつきが少なくなり、安心できる
現場での手作業は、どうしても、その日の天候や、作業する職人さんの経験、あるいは体調によって、仕上がりにわずかな差が生まれてしまうことがあります。しかし、工場製作の場合は、管理の行き届いた環境で、専用の機械や工具を使い、熟練した職人さんが集中して作業にあたります。そのため、誰がつくっても、いつつくっても、品質が安定しやすく、設計図通りの正確なものができあがります。配管からの水漏れなどの心配も少なくなり、長い時間にわたって建物を使う人々の、大きな安心につながるのです。
現場での作業時間が短くなる
現場での作業は、工場から届いた配管ユニットを組み立てていくことが中心になります。一本ずつ配管を加工していた頃に比べて、現場で過ごす時間が大幅に短縮されるため、工事全体の期間も短くすることができます。工事期間が短くなるということは、新しいお店や工場がより早くオープンできたり、改修工事で建物が使えない期間を短くできたりと、お客様にとってもうれしい結果となります。また、現場周辺に住む方々にとっても、騒音や振動、工事車両の出入りなどが気になる時間を、少しでも短くすることができるという利点があります。
働く人にとって、より安全で働きやすい環境に
建設現場には、高所での作業や、狭くて身動きが取りにくい場所での作業など、危険が伴う場面が少なくありません。工場製作という方法は、こうした現場での難しい作業を減らし、安全な工場内での作業へと切り替えることができます。足場が安定し、明るく、整理整頓された環境で働くことは、職人さんたちの身体的な負担を和らげ、怪我のリスクを大きく減らすことにつながります。働く人が安心して、健康に、そして誇りを持って仕事に取り組める。このことは、建設業界全体の未来にとって、何よりも大切なことだと言えるでしょう。
でも、気をつけなければいけないことも
ここまでお話ししてきたように、配管の工場製作には、品質の安定や工事期間の短縮など、たくさんの優れた点があります。しかし、この方法を成功させるためには、いくつか気をつけなければいけない大切なポイントも存在します。物事のよい面だけでなく、こうした注意点も知っておくことで、より深く理解することができます。
最初の「設計」が、すべてを決める
工場製作のいちばんの特徴は、あらかじめ工場ですべてをつくり込んでしまう、という点です。これはつまり、一度つくり始めてしまうと、後から大きな変更を加えるのが非常に難しい、ということを意味します。そのため、最初のパソコン上での立体設計が、工事全体の成功を左右する、きわめて重要な鍵となります。配管の担当者だけでなく、建物の構造を考える人、電気の配線を考える人など、関係者全員が早い段階から集まり、何度も話し合いを重ねて、お互いの計画を調整し、完璧な設計図を完成させておく必要があります。この最初の丁寧な準備を惜しまないことが、後の工程をスムーズに進めるための、何よりの近道になるのです。
運ぶこと、置くことの「ひと工夫」
工場でつくられた配管ユニットは、当然ながら、建設現場まで運ばなければなりません。ユニットがあまりに大きすぎると、道路の幅やトンネルの高さを通れなかったり、曲がり角を曲がりきれなかったりする可能性があります。そのため、設計の段階から、どのようなトラックで、どの道を通って運ぶのか、ということまで考えておく必要があります。また、現場に到着してからも、すぐに取り付けられるわけではありません。一時的にユニットを保管しておくための、十分な広さのスペースも確保しておかなければなりません。つくることだけでなく、それを「運び、置く」ことまで想像力を働かせる、細やかな配慮が求められます。
最後の「つなぎ」に心を込める
工場でどれだけ精密に配管ユニットをつくっても、それを現場で取り付ける際には、ほんの数ミリ単位のズレが生じることがあります。建物の柱や壁も、完璧な精度でできているとは限らないからです。そのわずかなズレを、現場でうまく調整しながら、最後の「つなぎ」の部分を丁寧に合わせていく作業は、やはり現場の職人さんの腕の見せ所です。工場での精密な作業と、現場での柔軟な対応力。その両方がそろって初めて、本当に質の高い配管工事が完成します。どちらか一方だけが優れていても、うまくいかないのです。
よい建物は、よい「チーム」から生まれる
配管の工場製作という新しい取り組みを成功させるために、最新の機械や優れた技術はもちろん大切です。しかし、それと同じくらい、あるいはそれ以上に重要だと言えるのが、人と人とのつながり、つまり「チームワーク」です。それぞれの専門家が、お互いを尊重し、協力し合うことで、初めて大きな力を生み出すことができます。
設計する人と、つくる人の「対話」
パソコンの画面上で立体図面を設計する人と、工場で実際に配管を組み立てる人。この二者の間での、風通しのよいコミュニケーションは非常に重要です。設計する人は、つくり手のことを考え、「どうすればもっとつくりやすくなるか」を想像します。一方、つくり手は、図面を見ながら「こうした方が、もっと品質が良くなるのではないか」といった、現場ならではの気づきを設計する人に伝えます。お互いが自分の仕事に閉じこもるのではなく、活発に対話を重ねることで、図面はより洗練され、できあがる配管ユニットの品質もさらに高まっていくのです。
工場と現場の「バトンパス」
工場で丁寧につくり上げられた配管ユニットは、いわばリレーのバトンのようなものです。工場チームは、そのバトンに「安全に、確実に取り付けてほしい」という想いを込めて、現場チームへと渡します。その際、ユニットのどの部分が壊れやすいか、どのように吊り上げれば安全か、といった細かな注意点を、しっかりと申し送ることが大切です。そして、バトンを受け取った現場チームは、その想いに応えるように、心を込めて取り付け作業を行います。工場から現場へ。このスムーズで確実なバトンパスが、チーム全体の信頼関係を築き、工事の成功を支えます。
経験と新しい技術の「融合」
長年の経験で培われた、ベテラン職人さんの鋭い勘や、言葉では説明しきれないような細やかな技術。そして、BIM(ビム)に代表される、パソコンを使った精密な設計・管理といった新しい技術。これからのものづくりでは、そのどちらか一方だけを重視するのではなく、両方の良いところをうまく「融合」させていくことが求められます。ベテランの経験が新しい技術の使い方を教え、新しい技術がベテランの技術をさらに高いレベルへと引き上げる。そうした良い循環が生まれるチームこそが、これからの時代に本当に必要とされる、強いチームだと言えるでしょう。
https://www.sakura2012.jp/recruit
ものづくりの「未来」を、工場から
これまで見てきたように、配管の「工場製作」という取り組みは、単に工事を効率的に進めるためだけの技術ではありません。それは、建設業界が抱えるさまざまな課題と向き合い、未来をより良いものに変えていこうとする、大きな挑戦の一つです。
工場という管理された環境は、建物の品質を安定させ、お客様に大きな安心を届けます。現場での作業を減らすことは、職人さんたちを危険から守り、より健康で、やりがいを持って働き続けられる環境をつくることにつながります。そして、それは若い世代の人々にとって、建設業界がもっと魅力的で、誇りを持てる仕事だと感じてもらうための、大切なきっかけになるはずです。
一つの建物を丁寧につくること。その先に、働く人々の幸せがあり、ひいては社会全体の豊かさがある。
ものづくりの拠点が、現場から工場へと少しずつ広がっていく。その変化の先に、私たちは、もっと明るい建設業界の「未来」を見つめています。


